 (前編)
(前編)
───不思議だね、
僕たちは、まるで巡り逢うために産まれてきたみたいなのに
あの頃の僕は、
大きな幸せと、そして小さな不安と両方を抱えていたんだよ
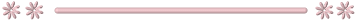
1.迷子
大手デパートの一角で、今優吾にとってとんでもない大事件が起きていた。
彼は、周囲が見えないほど気が動転し、何度も足がもつれそうになりながらも、何故か小さな少年を抱きかかえ、やっとの事で迷子案内所へと到着したのだった。
そして、到着して何の説明も無く、
「おねぇさんっ!!! 僕の華ちゃんッ、来てるでしょう!?」
「え?」
今にも泣きそうな優吾の顔。
それを見て、多少戸惑いつつも迷子案内所管轄のこの女性はにっこり笑い、
「迷子ですか? 今は一人もいませんが」
「・・・・・・っ・・・・・・う、うそ・・・・・・」
女性の言葉に更に追いつめられた優吾は、真っ青な顔になり今にも倒れてしまいそうな程の衝撃を受けた。
その様子があまりにも凄まじいため、女性は少々心配になってきた。
「あ、あの・・・アナウンスしますから落ち着いてくださいね」
「えっ!? 本当!? お願いしますっ、華ちゃんを助けてッ!!!」
藁をもつかむような気持ちになりながら、彼の言っていることは支離滅裂だ。
女性はアナウンスするだけで、華を助けることはできないのだから・・・
「とにかく、氏名と年齢、今日の洋服や髪型などの特徴を教えてください」
優吾は大きく頷くと、
「名前は、飯島華ちゃん、4歳。とびっきりかわいい女の子。ぱっちりしたおめめは二重で睫毛もくるんとカールしてるの。唇はちっちゃくてさくらんぼみたいで思わず食べちゃいたくなっちゃうっ、あとあとっ、髪の毛は薄い茶色の直毛でね、色白できめ細かい肌は将来絶対美人さんになると思うなっ、今は世界で一番カワイイけどね!」
「あ、あの・・・?」
「わかってるって、お洋服でしょう? お洋服はこの間一緒に買い物に行ったデパート・・・あ、ここじゃないんだ、ごめんね。とにかくそこで買ったチューリップ柄のワンピースを着てるの、それから、今日の髪型は二つに結わえて、耳の上を白いレースのおリボンで結んでるんだ。それって僕がやってあげるんだけどね、大体30分くらいかかっちゃうんだ。けど、今日は25分で出来ちゃった! 新記録だったんだよ」
「・・・わ、わかりました、では早速アナウンス入れますね」
「それだけでわかる? もっと詳しく言おうか?」
「いえ、大丈夫です」
「あっ!!」
「え? 何でしょうか」
まだ何かあるのだろうか、と女性が思っていると、優吾は今の今まで小脇に抱きかかえたまま忘れていた少年を思いだし、
「この子も迷子なの、一緒にアナウンスしてあげて!」
2.涙の再会
「おねぇさんっ、やっぱりあれだけじゃ華ちゃん見つからないんじゃないかなっっ、もうあれから結構経ってるのに・・・」
「大丈夫ですよ、落ち着いてくださいね」
このような問答は女性がアナウンスをかけてから既に3回目だ。
一分おきにこのような状態になり、ソワソワと非常に落ち着きのない様子の優吾は、見た目まだ高校生程度にしか見えない。
女性は父親にしては若すぎる容姿に、心の中で色々な疑問が渦巻いていたが流石に聞くことは出来なかった。
「なぁ、に〜ちゃん、そんなにオロオロしないでもアナウンスかけたんだから直ぐに見つかると思うよ?」
「あ、う・・・うん、だよね・・・でも、華ちゃんカワイイから、もしも・・・もしも誘拐されてたら・・・僕は・・・」
「ふ〜ん、に〜ちゃんの待ってる子ってそんなカワイイんだ」
「亮太クンッ!! 華ちゃんはね、世界一カワイイんだからねっ!! 亮太クンだって華ちゃんを見れば納得するよ!!!」
亮太というのは、優吾が抱きかかえていた少年のことだ。
この会話だけを聞いていれば、少年は優吾とそんなに年齢が変わらないように聞こえるかもしれないが、亮太はまだ立派な5歳児だった。
むしろ優吾の方にやや問題があるのかもしれない。
何故このような状況が起きてしまったのかは、小さな子供にはよくあることで、ずっと彼のズボンを掴んでいると思っていた華がいつの間にか今隣に座っている亮太にすり替わっていた事から始まっている。
亮太曰く、父親のズボンだと思っていたのに、気付いたら優吾のものだった、ということらしい。
どうやら今日の亮太の父親と優吾のズボンの色形などが似ていたようだった。
もしかしたら、華は亮太の父親と共にいるのかもしれないが、優吾にしてみればそれは全く確証のない期待でしかない。
この広いデパート内で迷子になって泣いてるんじゃないだろうか
もしかしたら怪しいオジサンに連れて行かれちゃったかもしれない
だって、華ちゃんカワイすぎるから
心配はどんどん膨らみ、優吾の胸は苦しくて潰れそうだった。
もうこんな所でじっとなんてしていられない、探しに行こう!
そう思ったときだった。
「あっ、パパだ〜♪」
かわいらしい声が聞こえ、優吾と亮太はその方向を一斉に見た。
そこには、男性に手を引かれた少女が嬉しそうに笑いながら近づいてくる。
それは紛れもなく・・・
「華ちゃん!!!!」
優吾は全速力で華の元に駆け寄ると、ガバッと抱き上げ何度も何度も頬ずりをする。
「華ちゃんっ、無事でよかったッ、僕死んじゃうかと思った〜!!」
「はうっ」
思いきり抱きしめられて、華は苦しさのあまり目を白黒させているが、優吾は涙まで浮かべて今華が腕の中にいることに安心しきってしまい、腕の力を緩めることを忘れていた。
それを見た男性が、
「涙の抱擁も程々にしないと、大事なお嬢さんが苦しがってますよ」
「あっ」
その声にやっと正気に戻った優吾は腕の力を少し緩め、華は解放されて、はふはふと息を吐く。
「ごめんね、ごめんね華ちゃんっ」
ひたすら華に謝り、ふと、隣に立っている男性に目をやり、優吾はそこで初めてその男性について考えを巡らした。
「あぁっ、華ちゃんを連れてきてくれてありがとうございますっ、ホントに何てお礼を言ったらいいか・・・・・・っ、ホントにホントにありがとうございますっっ!!!」
「いいんですよ、そんなのはお互い様ですからね。どうやらウチの亮太もお世話になったようですし。・・・あぁ、やっぱりズボンが原因だったんですね、華ちゃんが言ってた通りだ」
「あ・・・」
そう言われ、改めて見ると、二人の履いているズボンの色や形などよく似ている。
それに背格好や体型なども大体同じくらいだろうか。
華や亮太の目線で見ればズボンの色で認識していてもおかしくはないのだ。これではちょっと目を離した隙にこういう事が起こっても不思議ではないだろう。
「・・・・・・なるほど〜」
男性は頷きながらにっこり笑い、華に視線を移し、頭をふんわりと撫でた。
「パパが見つかって良かったね」
「ウンッ!」
嬉しそうに笑い、優吾の首に腕を回してしがみつく様子に目を細めると男性は亮太の手を取る。
「亮太も無事で良かった」
「当たり前じゃんっ、おれなんてこのに〜ちゃんのお守りで大変だったんだからな」
「こらっ」
「だってホントのことだも〜ん」
あっかんべ〜と舌を出しながら亮太の言っていることはあながちウソではない。
その様子を見ながら、優吾は思いついたように顔を輝かせた。
「あのっ、お時間あったらコーヒーでも一杯飲んでいきませんか?」
3.デパート内の喫茶店にて
「それじゃ高橋サンの奥さんは赤ちゃん産んだばかりで里帰りしてるんですね。じゃぁ、亮太クンはお兄ちゃんになるんだぁ」
「ええ、お腹に赤ん坊がいる頃から自覚があるのか急に成長した気がしますね」
優吾はその情景を思い浮かべて、頷きながら微笑みを浮かべた。
彼らの会話の横では、華と亮太がチョコレートパフェを頬張りながら、早くも打ち解けて楽しげにしている。
それを横目で見ていると不意に亮太の父親が優吾に問いかけてきた。
「あなたは? まだ随分若いようだけど」
「え? あぁ、若く見えます? これでも大学4年生だから、もうすぐ卒業なんですよ〜」
「大学生!」
彼は目を見張り思わず大きな声を出してしまい、直ぐにハッとして口を押さえながら恥ずかしそうにはにかんだ。
「・・・イエ、失礼。確かに見た目だけなら高校生にも見えたのですが、お子さんがいるくらいだからてっきり社会人かと思ってました。人には色々事情がありますからね、スミマセン」
「いいんですよ〜、大した事情じゃないですから。ただ、僕には奥さんはもういないけど、華ちゃんと一緒にいられるって事が何よりの幸せだから」
ふんわりと笑う優吾の表情に嘘はない。
その年で大学に通いながら子供を1人で育てるというのは並大抵の努力で出来るものではない。本当に子供を愛していても、大変な労力だ。
妻が里帰りして、現在1人で息子を見ている彼にはそれが身にしみて分かる。
「い〜な、オマエはおれの奥さんになるんだぞっ!」
「え〜っ」
「え〜っ、じゃないっ! おれは決めたぞ!」
突然聞こえてきた会話に男性と優吾は顔を見合わせた後、華と亮太に視線を向けた。
今聞こえてきたのが空耳でなければ、何だかとんでもない内容だった気がする。
内心優吾は動揺しながら、話の中身を把握しようと必死で聞き耳を立てた。
「おくさんってなぁに〜」
「オマエそんなことも知らないのか? いいか? 奥さんっていうのは、おれと一生愛を誓い合うおんなのことだ」
「ふ〜ん、ソレって楽しいの?」
「楽しいぞ、オマエが望むなら毎日ゆ〜えんち連れてってやっても良いぞ! おれがオマエを養ってやる、おれは将来大会社の社長になってる予定だからな!」
「わぁ〜」
華はよく分からなかったが、遊園地という言葉にすっかり魅了されて、奥さんってスゴク素敵なものだと思っている様子だ。
優吾は子供同士の他愛もない会話だとは思いつつ、それを温かく見守るという芸当が出来なかった。
「り、亮太クンッ! 華ちゃんはあげられないよっ!!」
「なんでだよ〜っ、い〜じゃん、減るもんじゃないんだし」
「減るとか減らないとかじゃないのッ! とにかく駄目なものは駄目ッ!!」
「やだよ〜、だって、おれ華のこと気に入ったもん。に〜ちゃんの言うとおりコイツ、カワイイじゃん」
「あっ、やっぱし?」
と、一瞬亮太に華を誉められて嬉しくなってしまった優吾だったが、ふるふると首を振って会話の軌道修正を試みた。
「と、とにかくねっ、華ちゃんは亮太クンのお嫁さんにはあげられないのっ、そんなっそんなっ、僕は、華ちゃんと離れるなんて・・・っ、そんなのは考えたくもないよっ! だからっ、お願い、華ちゃんを連れてかないで」
目をウルウルさせて、5歳児に懇願する様子は非常に面白いものがあるが、本人は至って真面目だった。
端から見ても優吾の華への溺愛ぶりは相当なものがあるが、本人はそれ以上に自分自身を自覚しているから余計に手に負えない部分がある。
優吾と亮太の会話を首を傾げながら聞いていた華は、急に何か合点がいったらしく顔を輝かせながら優吾の腕に抱きついた。
そして、
「わかったっ、奥さんってお嫁さんのことなんだっ! 華ね、パパのお嫁さんになるってやくそくしてるから亮くんのお嫁さんにはなれないの」
「エ〜〜〜っ!? なんだよそれ〜〜〜っ!!」
にっこり笑った顔は無邪気なものだった。
だが、実のところ、華は『お嫁さん』も『奥さん』もちゃんと理解はしていない。
というのも、これには少し前に二人で風呂に入ったときに交わされた会話が起因していたからだ。
それは、湯船に浸かり、幼稚園で流行っているという子供向けの歌を一曲歌い終わった後だった。
『なんで華にはママがいないの?』
と、華が突然前触れもなく優吾に聞いてきた。
どうやら幼稚園で友達との会話の中でママという言葉が多く出てきて、華にとって一度も会ったことのない母親の存在はよく分からなかったものの、何故他の子供には当然の如くいるものが自分にはいないのか疑問を持ったらしかった。
優吾は一瞬困ったなぁというような表情を作ったが、正直に話すことにした。
『ん〜、僕にはお嫁さんがもういないからねぇ・・・』
『お嫁さんってママのこと?』
『そうだよ』
すると、華はちょっと考えるような仕草をして、その後泣きそうな顔になりながら優吾に抱きついた。
優吾は、華を泣かせてしまったと思い焦ったものだが、彼女から出てきた言葉は全く思いもよらないものだった。
『パパかわいそう・・・華がパパのママになってあげる』
『え?』
『華がパパのお嫁さんになってあげるね、パパを守ってあげる』
ぽろぽろと大粒の涙を零しながら一生懸命抱きついてくる華の姿に感極まった彼は、一緒になってオイオイ泣いてしまった。
幼い子供というのは時に信じられないくらいの包容力を見せる。
物理的にこんなに幼い子供が親を守るということは不可能だが、『守ってあげる』などと自信満々に言ってのけたりする事があるのだ。
それは、親にしてみれば、涙が出るほど嬉しい言葉で、その上、物理的には無理でも、何だか精神的に守られたような気がするのが不思議なところである。
華の中では、『お嫁さん=優吾のママ』になっていて、今はそれが『奥さん』とも同列の言葉なのだと解釈したに過ぎない。
ちなみに、彼女は『パパ=お父さん』ということを理解していても、『ママ=お母さん』ということを理解していないので、友達との会話でも時折とんちんかんな受け答えをしているらしい。母親という存在を全く知らない彼女にとって、それがどういう役割を持つ者かを理解するにはまだ早すぎるようだった。
だが、
優吾はそんな華の言葉に涙が出そうなほど感激していた。
嬉しすぎて、華をギュウギュウに抱きしめて何度も頬ずりを繰り返す。
「華ちゃ〜ん、僕は世界で一番の幸せ者だねぇっ」
「あんっ、パパ〜、あんまりぎゅってしたら苦しいよぅ」
「あっ、ごめんねっ、もぅ僕ってば華ちゃんのこと大好き過ぎて困っちゃうなぁっ♪ 好き好き大好きっ、食べちゃうからっ、あむ〜」
口をパクッと開けて、華の頬にかぶりつくような動作をしながら、人目を気にせず何度も『ほっぺにちゅ〜』をする優吾。
こうなるともう彼を止められる者は誰もいない。
華もくすぐったそうにしながら、とても嬉しそうに優吾の激しすぎる抱擁を受け止め、その様子を見た亮太は『ちぇっ』と呟き彼の父親と共に苦笑するしかなかった。
大人が子供になってしまうと、子供は大人になるしかないようである。
後編に続く
Copyright 2003 桜井さくや. All rights reserved. Never reproduce or republicate without written permission.