明くる日、蘭は一日中ぼんやりしていた。
禎一に処女を犯された時もそうだった。
やはり初めて肛門を犯されてしまったことが効いているのだろうか。
それとも、豹変した彼の態度についていけなかったのかも知れない。
いずれにしても蘭らしくなかった。
廊下の開放された窓際に立ち、意味もなくグラウンドを見下ろしている。
何を見るということもなく、視線は虚ろだった。
「どーした、どうした!」
突然、背中をどんと叩かれた。
驚いて振り返ると、園子がにっこり笑っている。
園子は気さくに蘭の背を抱き、言った。
「何をぼーーっとしてんのよ、あんたらしくもない。まるでおばあちゃんみたいな顔
してるわよ。若さがないぞ」
そんなことを言われたのは初めてである。
さすがに心外だったのか、蘭は少し拗ねたような顔で言い返した。
「何よ、ご挨拶ね。花の女子高生を捕まえておばあちゃんはないでしょ」
「そう言われたってしょうがない顔してんのよ、あんた」
「そう……かな」
「そうよ」
そこで園子は蘭の背から手を外し、両手を腰に当てた。
何だか堂々としている。
今の蘭とは正反対だ。
屈託のない態度や気安さからは感じ取れないが、園子はセレブの娘である。
なのに本人はそれをまるで鼻に掛けておらず、見た目も仕草も蘭たち庶民の娘とまったく
変わらない。
園子は蘭の親友だと自覚しており、そう振る舞ってもいる。
それだけに、ここしばらくの蘭の変節振りには気を揉んでいたのだ。
園子はまた蘭の背に手を回し、そして廊下の隅まで導いていく。
蘭は戸惑いの表情を浮かべた。
「な、なに園子……、どうしたの?」
「どうしたの、じゃないわ。今言ったでしょ、あんた最近ヘン」
「そ、そう……かな……」
「そうよ」
園子は蘭の肩を抱きながら言った。
心配そうな声で園子が聞く。
「やっぱ、あれ? こないだ嵯峨島のやつに呼び出された件」
「あ……」
「そうだろ? あいつ、あんたに因縁着けて来たんじゃないの? だって、そうじゃ
ない。あんたは生活指導の教師に呼び出されるような子じゃないもの」
「そうなんだけど……」
どうも蘭の顔色が良くない。
園子はうつむき加減の蘭を覗き込むように言った。
「何よ!? あのバカ、どんな言いがかりつけてきたの?」
「うん……」
「言いなさいよ。場合によっちゃ、あたしが……」
「わかった、言うから」
蘭は軽くため息をついた。
ここで口ごもったり誤魔化したりすれば、園子が暴走しかねない。
園子の場合、親のこともあるから、そうそう嵯峨島も無茶なことは出来ないはずだが、
それでもあまり目立たせるのもまずかった。
蘭は少し言い淀んでから、そっと園子に耳打ちした。
ふんふんと聞いていた園子の顔が一変した。
眉は逆立ち、目を剥いている。
「援助交際ですってぇっ!?」
「そっ、園子、声が大きいっ」
蘭が慌てて園子の口を手のひらで塞いだ。
むぐむぐ言っていた園子はその手を引き剥がし、憤懣やるかたないと言った様子だ。
声を殺して怒鳴っている。
「援助交際……エンコー? 蘭がエンコーしてるっての!? バッカじゃないの、
あの男! 蘭なんて、ウチの学校でいちばん援交とほど遠い子じゃないの! なに
考えてんのよ!」
「園子が興奮することないでしょ」
「興奮するわよ! 怒って当然でしょ! だいたい、あんたはなんでそんなに冷静
なのよ! こんなバカバカしい、しかもしっつれいな疑いかけられて!」
「そうなんだけどね……」
「ちょっと、あんた」
園子がじっと蘭を睨んでいる。
目が座っていた。
「なんでそんな弱気なのよ、あんたらしくない。まさかマジで……」
「そんなわけないでしょっ!」
「だったら何よ? とんでもない言いがかりなんだから、言い返せばいいのよ」
「ん……、実はね……」
また蘭が園子の耳元に口を寄せて囁く。
今度は園子の顔が曇った。
「え? じゃあ、あんた見られてたんだ……」
「みたい……」
園子が早口で言う。
「だから言ったでしょ、もういい加減にしなさいって」
「……」
「人が良いにも程があるわよ。なんであんたが森先輩の面倒みなきゃいけないの」
「だって……」
「ええ、ええ、確かに森さんの身の上や西園さんのこととか、同情したくもなるわ。
面倒見のいいあんたなら余計にそうでしょうよ」
「……」
「でも、それにしたって、こう何度も続けて彼のアパートに行ったりするからそんな
疑いかけられるのよ。まさか、あんた……」
「な、なに?」
「まさか、森さんのこと……」
「ち、違うわよ、変なこと言わないで!」
「……」
「な、何よ、その目。信用しないの? あたしが本気で、その、森さんを好きになった
と思ってんの!?」
「……んなわけないよね。新一くんが……」
「わ、わかってるなら、そんなこと言わないでよ」
「あたしはわかったわよ。でも、それを見た嵯峨島の野郎が邪推したってわけなんで
しょ?」
「そう、みたいね……」
さすがに園子も困ったような顔をして腕組みした。
「もうやめなさいと言ってもやめないんでしょ?」
「……」
「仕方ないわね……。あんた、妙なところで頑固なんだから」
園子は少し考えてこう言った。
「じゃ、こうしましょ。少し頻度を落とすのよ。今、どれくらいのペースで森さん
とこに行ってるの?」
「んーーー……、決まってないけど、森さんから連絡が来たらって感じ。週に二三度
かな……」
「そんなに?」
園子は呆れた。
せいぜい週に一回程度だと思っていたのだ。
「それじゃペースを落としなさい。せいぜい週に一回くらいに。それと」
「?」
「その時はあたしも呼んで。一緒に行くから」
「え、でも……」
「いいから。さすがにあたしとふたりで行けば、それを見てもバカな勘ぐりはしない
でしょ」
「や……、でも、いいよ、園子」
「何でよ。あたしが行っちゃ都合悪いの?」
「そう言う訳じゃないけど……」
「じゃ、そうなさい。いいわね」
「……」
蘭の口からは何とも言えないのだ。
すべて禎一の指示によって動いている。
そこに園子を連れて行ったりしたら、その場での蘭への凌辱はしないかも知れないが、
その後、どんな仕置きをされるかわかったものではない。
またぞろ恥ずかしく、いやらしいことをされるに決まってるのだ。
いや、ヘタをしたら園子まで巻き込むことになるかも知れない。
だが、この場で断っても園子はついてくるだろう。
取り敢えず承諾するしかなかった。
禎一に頼んでどうなるかはわからないが、何とか懇願して自分ひとりで済むように
しなければならない。
そんなことを考えている時、蘭の携帯が鳴った。
慌てて周囲を見回す。
蘭は携帯の液晶を確認してから電源を切った。
「あ……、園子、ちょっとあたし、行ってくるから」
「は? 行くって何よ。どこ行くのよ、まだ昼休み終わってないわよ。今の携帯?」
「うん……まあ、そんなとこ。ありがと、園子。いろいろ心配してくれて」
「いいけど……」
園子はまだ不得要領な顔だ。
それでも蘭が気丈に振る舞っているのを見て、敢えて笑顔を浮かべた。
「ま、あんたがそう言うんならね。ほら、どこ行くか知らないけど急いだ方がいいん
じゃない? 午後の授業、欠席するつもりじゃないんでしょ」
「あ、うん」
園子は、蘭の背中をポンと叩いて送り出した。
蘭の背を見送りながら園子は考えた。
何だか変だ。
よくよく考えてみれば、蘭が森のアパートへ通うところを見られたとしても「援助
交際」だとは思わないだろう。
普通は「不純異性交遊」だと疑うのではないだろうか。
どちらも女学生が身体を提供することに変わりはないが、片や恋人同士や親密な関係
の末のことだろうし、もう片方はズバリ売春だ。
学年が上とはいえ、同じ高校生同士がつき合ったとして(蘭は森とつき合っている
わけではあるまいが)、それを援助交際というのはおかしいだろう。
嵯峨島は何を考えているのだろうか。
小走りに駆け出す蘭の姿を見ながら、園子は首をかしげて手を何度か閉じたり開い
たりした。
まだおかしいところがある。
「ん?」
自分の手のひらを見てみる。
何だか、さっき蘭の背を叩いた時の感じがヘンだったのだが、その原因がわからない。
「あ……」
急に思いついたように園子は蘭の行った後を目で追った。
制服越しにストラップの感覚がなかったのだ。
「あの子……、ブラしてなかった……のかな? ヌーブラ? そんなもん着けるタイプ
じゃないけど……」
────────────────────────
南校舎一階、教員職員用の男子トイレ。
個室が三つと小便器が四つ、洗面台が三つのこぢんまりしたスペースだ。
職員室や校長室にもほど近いここには、滅多なことでは生徒は近づかない。
職員室に用事はあっても、わざわざ教師専用のトイレには入らない。
その男子トイレの一角、いちばん端の個室でくぐもった声と物音が聞こえてくる。
「あっ……!」
禎一は蘭を壁に押しつけて凄んだ。
制服とカッターシャツの胸ははだけられ、スカートまでめくり上げられている。
その胸はブラジャーをしていないから、もろに乳房が零れている。
禎一の顔つきも口調も、最初の時とはまったく違っている。
「蘭、これはどういうことだよ!」
「あ……」
「ショーツなんか履きやがって! 俺は言ったよな、ブラもショーツも着けないで
来いと!」
「あ、で、でも下着なしだなんて……。ブラしてないだけでも、恥ずかしくて死に
そうなのに……」
「ふざけるな!」
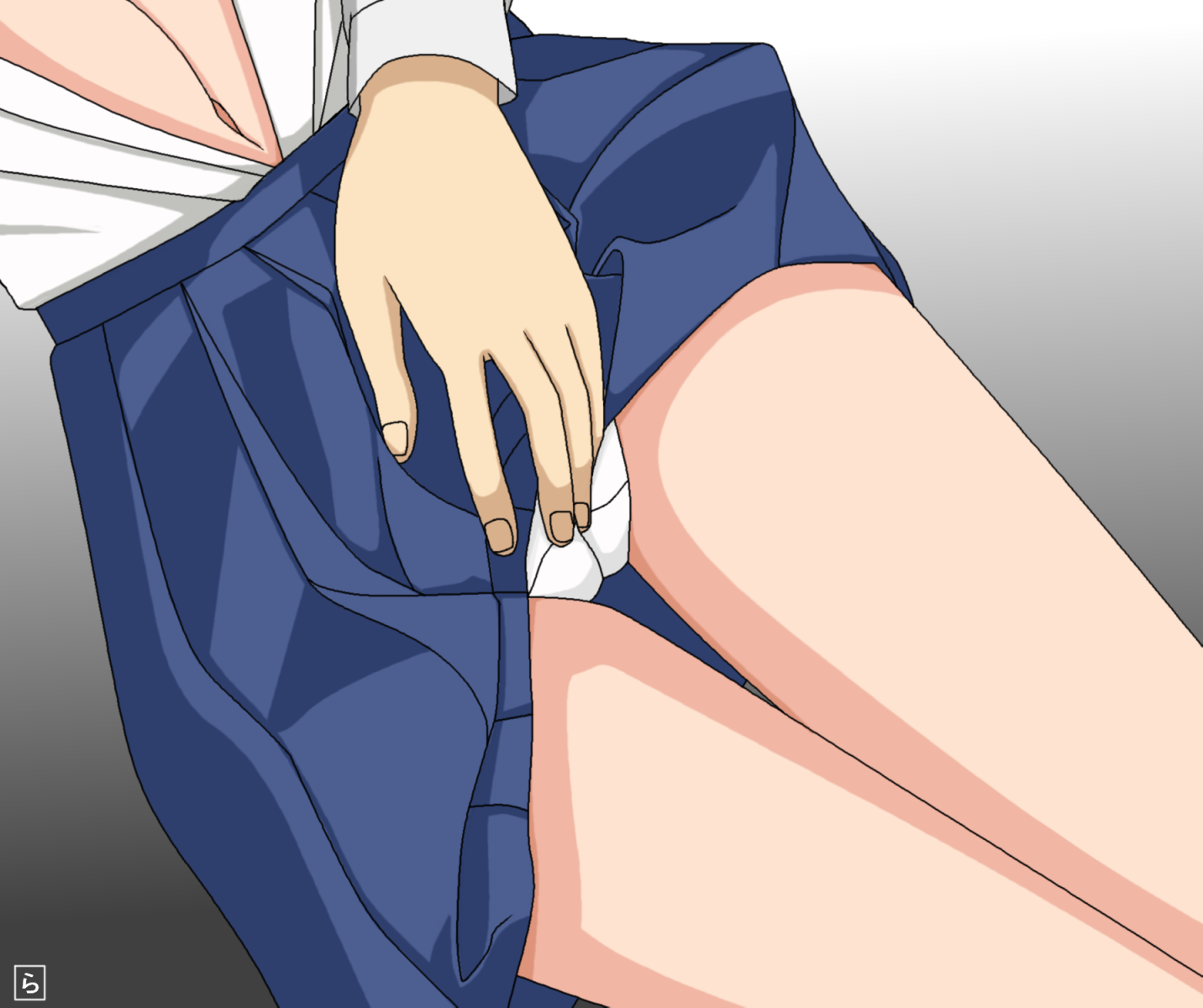
禎一にしてみれば飼い犬に手を噛まれたようなものだ。
激昂した禎一は、怒りにまかせて蘭の左右の頬をバシッ、バシッと張った。
さすがにカッとした蘭は、キッと禎一を睨んで殴り返す。
ぱぁんと乾いた音がして、思わず禎一は右頬を押さえた。
なぜか禎一はにやっと嗤った。
気丈なのは知っているが、ここまで活きが良いとは思わなかった。
普通、あそこまでレイプしてしまえば、もう女は言いなりだった。
蘭も女の子だからそうした面もあるにはあるが、やはり勝ち気なところが顔を出すのだ。
「……痺れたぜ、蘭。この期に及んでまだ楯突くとはな」
「……大声出しますよ」
「……ほう」
「いいんですか、ここ職員トイレなんですよ。ここであたしが大声で叫べば、絶対に
職員室に聞こえます。踏み込まれますよ」
「いいよ」
「え?」
禎一はフッと嗤った。
「そうしたければすればいいさ。先公どもがここに駆けつけてきたら事件だよなあ」
「そ、そうですよ。森さん、ヘタしたら停学……いえ退学ですよ!」
「それだけじゃない、警察沙汰にでもなれば強制猥褻ってところかな」
「わかってるなら……」
「でもさ、俺より蘭の方が困るんじゃない?」
「……」
「いいよ、俺は自首して逮捕されるよ。そんでもって、洗い浚い蘭を犯したことを
喋ってやる。どんなプレイをしたのか、それで蘭がどう反応したのかもな」
「……」
「感じまくっていっちまったことも臨場感たっぷりに供述してやる。オマンコだけ
じゃなく尻の穴まで……」
「やめて!」
忌まわしい言葉に、蘭は耳を塞いだ。
禎一は蘭を壁に押しつけ、その顔の脇に腕を突いて顔を近づける。
「わかったろ? もう俺に従うしかねえんだよ。な?」
「……」
「それはそれとして、だ」
男の口調がまた低く変わる。
「あれほど俺の言うことは絶対だと言ったのにこれか。まだよく自分の立場がわかって
ないようだな」
「……」
「……仕方ねえ、仕置きをしてやるからな」
「し、仕置きって……あっ!」
禎一が蘭の上着を掴み、ぐいっと開いた。
ただでさえはだけた制服の胸をさらに大きくさらけ出されると、蘭は小さく悲鳴を上げ、
慌てて両手で胸を隠そうとする。
その腕が男に掴まれた。
禎一はベルトに挟み込んでいたロープを取り出すと、手際よく蘭の両手を縛り上げた。
その手慣れた様子を見ると、こうして女を縛っていたぶるのも初めてではないのだろう。
「な、何をするんですか!」
蘭が抗議する間にも、てきぱきと拘束していく。
両手首をひとまとめにして縛り上げると、そのロープを壁から生えている太いパイプに
引っかけた。
そのままぐいとロープを引くと、蘭はたちまち爪先立ちになってしまう。
さらにこの不良学生は、ばたつく蘭の右脚を抱え持つと、するっとショーツを脱がして
しまった。
下着から右足を抜かせ、もう一本のロープを膝に引っかけて、それも同じように壁の
パイプに通して釣り上げた。
こうして蘭は、両手で上から爪先立ちに吊られ、右足の膝が大きく上がって脚を開く
格好になっている。
右足の膝が右の乳房にくっつくほどに開脚されていた。
蘭は激しく動揺した。
「こ、こんな……縛るなんてひどい……」
「蘭が俺の言うことを聞かなかった罰だよ」
「あ、許して……もう、もう逆らいませんから……」
「よし、それでいい。だがな、そうやってパンツ履いてきた罰と、さっき俺をひっぱ
たいてくれた礼もしてやるぜ」
「ああ……」
「くく、たっぷり可愛がってやるからな。せいぜい反省しなよ」
蘭は気が気ではなかった。
初めての緊縛、それに加えて場所が場所である。
よりによって学校で辱めを受けるとは思わなかった。
しかもトイレの中だ。
職員トイレだからそうそう人は来ないはずだが絶対ではない。
来てしまったら、それも「行為」の最中に来てしまったらどうなるのだろう。
もしバレてしまい、ドアをこじ開けられたら、これ以上ない恥ずかしい姿と行為を見ら
れることになる。
「いい格好だな、え、蘭」
「いや……許して、見ないで!」
禎一が屈んで蘭の股間を覗き込んでいる。
ロープで吊られてしまっていて、脚を閉じることも出来ない。
見たところ、もう濡れ始めている。
淡い陰毛はじっとりと露を含んでいるように見えた。
まだ愛撫などまったくしていないのにこれだ。
蘭が淫乱とかそういうことではなく、こういう異常で倒錯的な状況に対して興奮して
しまうのだ。
普段は清楚で、それでいて男勝りであるだけに、こうした責めには取り分け弱いよう
だった。
禎一はそんな蘭の性格を利用し、さらに追い詰めていく。
身を屈めて、大きく開かれた蘭の股間に顔を寄せたのである。
少女は激しく動揺した。
「い、いやっ! 見ないで、そ、そんな近くで見ないで!」
「蘭、声が大きい」
「……!!」
禎一は手を伸ばして蘭の口を塞いだ。
蘭もハッとして口をつぐむ。
確かにここで悲鳴を上げれば、「何事か」と教師が駆け込んでくるだろう。
そうなったら蘭にとっても身の破滅だ。
そっと男が手を離しても、もう蘭は大声を出すことは出来なくなった。
それをいいことに、禎一はまた蘭の秘部をじっくりと観察している。
顔がくっつかんばかりに近くから食い入るように見ている禎一の視線を受け、蘭は
激しい羞恥で打ちのめされていく。
「見……ないで……ああ、いやあ……」
「相変わらず綺麗だな、蘭。本当にまだ処女みたいだ……。もう散々俺に犯された
ってのにな」
「言わないで……ああ、見ないで、恥ずかしい……あ、触っちゃだめっ」
禎一は蘭のそこの構造を調べるかのように、指で丹念にまさぐり、ほじくっていった。
やはりもう愛液がだいぶ分泌されている。
恐らく、ここへ来る前から濡れていたのだろう。
ブラをしていない、それを誰かに知られたら……という恐怖と羞恥が、この少女を
性的に昂ぶらせていたに違いなかった。
まさぐる禎一の指にも熱い蜜がねっとり絡んでくる。
クリトリスも包皮から顔を出しかけ、尖り始めていた。
もうたまらなくなって、禎一はそこに口を寄せて吸い付いていく。
蘭は仰天し、その腰が跳ねた。
「ひぃっ! そ、そんなことしないで、ああっ!」
「声がでかいって言ってるだろ。いいのか、先公に踏み込まれても」
「だ、だって、ああっ、そんなことされたら……」
「どうなるってんだ。感じすぎて喘いじゃうってか」
「やっ……あ、しないで、あうっ……」
蘭は必死になって声を殺している。
どうしても漏れてしまう喘ぎを噛み殺し、懸命に唇を噛みしめているのだが、あえ
やかな呻き声が出るのは止めようがない。
その時だった。
「!」
人の気配がしたのだ。
さすがに禎一も動きを止めた。
ゴム底の靴がタイルを叩く音がする。
その足音は小便器方面には向かず、個室の方へ向かってきた。
蘭はもう生きた心地がしなかった。
蘭と禎一が籠もっている個室は当然ドアを閉めており、内鍵を掛けている。
使用中だと思うはずだ。
残りふたつが空いているのだから、まさかそこへ来るはずはなかったが、足音が近づく
だけで蘭の肝が縮み上がる。
蘭たちはいちばん奥の個室にいたが、入ってきた男はいちばん出入り口よりの個室に
入った。
3つの個室があって、右端に誰か入っていれば、普通はその隣ではなく左端に入る
だろう。
その教師もそうしたらしい。
蘭は少しホッとした。
隣に入られたら、ちょっとした物音でも不審に思われてしまうかも知れないのだ。
しかし、そう安心してもいられない。
ここにまた誰か入ってきて、その人も個室を使おうとすれば、どうしたって蘭たちの
隣に入るしかないからだ。
不幸な美少女は心で震えながら、そうならないことを祈っていた。
その蘭の切なる願いを打ち砕くかのように、禎一は彼女の媚肉を口で愛撫していく。
「くうっ……!」
鋭い快感が膣から腰の奥へと突き抜けていく。
禎一はわざとぐちゅぐちゅと淫らな音をさせながら、蘭の媚肉を吸ってくる。
蘭は気が気ではなかった。
「そ、そんな音させないで! あ、あう……」
声を殺して無声音でそう言うのだが、その言葉も喘ぎに飲み込まれていく。
どう我慢しても、蘭の肉体は禎一の唇と舌の愛撫に対して鋭敏に反応してしまう。
膣内の襞がひくつき、奥からじわっと熱い蜜が湧いてくるのがわかる。
禎一は両手で蘭の尻を抱えて撫で回し、舌先を尖らせて膣の中に挿入し、その中を
舐め回している。
蘭の顔がグッと反り返ったり、「んんっ」と呻き声を堪えている様子を確認しながら、
禎一は舌でぺろりとクリトリスを舐め上げた。
「んあっ!」
思わず蘭は堪えていた声を上げてしまい、慌ててまた口をつぐんだ。
そしてクンニしてくる禎一の方を潤んだ瞳で見ながら「もうやめて」と無言で訴える。
しかし男がやめるはずもなく、禎一はにやりと嗤って、さらに責め上げていく。
いったん口を離したものの、またすぐに吸い付いていく。
舌でねっとりと割れ目の内部を舐め回し、また舌先で膣を犯す。
そして唇でクリトリスを軽く挟むと、ちゅるっと思い切り吸引した。
どろりと愛液が零れてくる。
「ひぐぅっ!」
蘭の顔が大きく仰け反り、大きめの呻き声が迸った。
運良く、ちょうどその時に水洗の音がした。
その水音で蘭の悲鳴はかき消され、使用者も気づかなかったようだ。
そしてバタンとドアを開閉する大きな音がして、誰かが出て行く靴音が聞こえた。
出て行ったようだ。
「ああ……」
蘭はホッとしたように全身から力を抜いた。
まだ禎一が媚肉を舐めているが、その快楽よりも安堵した気持ちの方が強い。
これから見ても蘭はやはり、誰かに見られる、知られてしまうかも知れないという
恐怖が、官能中枢に強い刺激を送っているようだ。
禎一は立ち上がって蘭の腰を抱いた。
露出された乳房を軽く揉みながら、蘭の耳元で言う。
「……行っちゃったね。バレずに済んだよ」
「ひどい……、ひどいです。もうこんなことやめてください……」
「今さらやめられないよ。これは言うことを聞かなかった蘭への罰なんだからね」
「そんな……、ああ、謝ります、謝りますから……」
「じゃあ、今度からは必ず俺の言うことは守るんだね?」
「は、はい……。だからもう、今日は許して……」
「だめ」
「そんな……」
「さっき蘭にビンタされた仕返しもあるし、それにもう蘭のこことはこんなになっちゃ
ってるじゃないか」
「ああっ、さ、触らないで!」
「ここまできたら、もう突っ込まれないと満足できないでしょ?」
「そ、そんなことないっ……だからもう………」
「しっ!」
気配を感じて、禎一は咄嗟に蘭の口を塞いだ。
蘭は禎一の手の下でもごもご言っていたが、すぐにビクッとしておとなしくなった。
彼女も人の気配を感じたのだ。
ぺたん、ぺたんというサンダルのような音が複数聞こえる。
ぺたたん、ぺたん、ぺたんという感じだ。ひとりではないらしい。
蘭だけでなく、禎一も息を潜めて様子を窺っている。
薄い扉を通して男の濁声が聞こえた。
「やっぱ、それはまずいですよ、嵯峨島先生」
「どうってことありませんわ。それくらい日常的なことでしょうに、田中先生」
蘭は「ひっ」と喉を鳴らした。
よりによって嵯峨島のようだ。
もうひとりは二年の学年主任である田中教諭らしい。
ふたりは小便器の方へ歩いて行ったようだ。
蘭は息を殺していたが、なぜか禎一はにやっと嗤っていた。
「女生徒たちが何度が私んとこに来たんですわ」
「私のことでですか?」
「まあ、そうです。水泳の授業とか、部活の時に嵯峨島先生が、その……」
「じろじろ見ていていやらしい、とか?」
「……そんなところです。だから注意してやめるように言ってくれ、と」
「はっ」
嵯峨島は鼻で笑った。
「そんなこと気にすることないですわ。いや、見ていない、それは誤解だという
つもりはありませんよ」
「じゃあ……」
「ええ、見てますよ。いけませんかね?」
「……」
それはいけないだろう。
教師たるもの、教え子をそんな目で見るというのは冒涜的な行為である。
「でも見てるだけですからね。別に手を出したわけじゃありません」
「嵯峨島先生、滅多なことを言うもんじゃありませんよ」
身を固くしながらそんなやりとりを聞いていた蘭は、禎一がスラックスとトランクスを
脱ぎ去ったのを見て青ざめた。
まさか、こんなところでするというのだろうか。
「やっ……、ま、待って、ちょっと待って!」
小声で蘭は必死に抗った。
なのに禎一は、まるで見せつけるように自分のペニスを持ってぶらぶらさせている。
「待てないね。もう、こんなになっちゃってんだ。蘭だってそうだろうに」
「ゆ、許して! それだけは……、ああ、今はやめて……」
「くくっ」
蘭の懊悩ぶりを楽しむかのように、禎一はその腰を抱え持った。
ぐいと自分の方に引き寄せると、すべすべした腿に肉棒を擦りつける。
蘭は喉の奥で悲鳴を上げながら、何とか逃げようと身体をうねらせているが、縛られて
いてどうにもならない。
蘭の太腿にカウパーをなすりつけて遊んでいた禎一は、脅える美貌を眺めつつ、肉棒を
媚肉にあてがった。
「だめっ……!」
熱く滾り、潤みきった媚肉は硬いペニスを迎え入れ、じわじわと挿入されていく。
釣り上げられた右足をくねらせながらのけぞり、蘭はくぐもった呻き声を漏らした。
「ぐっ……、あ、うむっ……!」
ゆっくりとだが、確実に熱くて太いものが潜り込んでくる感覚に、頭の中がカァッと
灼けていく。
片足吊りで、その膝が乳房を潰すくらいの窮屈な姿勢で貫かれたせいか、いつも以上に
きつさと圧迫感を感じた。
「あ、あうむ……いや……んむっ!」
「そうら全部入った。くく、どうしたんだ、いつも以上に締まりがいいぜ、蘭」
そう言って蘭の顔を覗き込むと、少女は懸命に唇を噛みしめ、苦しげに喘いでいた。
禎一は意識を外の嵯峨島たちへ持っていく。
蘭の悲鳴は小さかったが、それでも気配でバレる可能性もある。
幸いふたりとも自分たちの話に集中してしまい、あまり周囲を気にはしていないようだ。
嵯峨島の声がする。
「それにですな、田中先生。若い女の子のぴちぴちした姿をナマで見られるなんて
のは、我々教師の特権みたいなものじゃないですか」
「い、いや……」
「そうじゃありませんかね? クソ生意気な生徒どもや小うるさい親たち、それに
目障りな校長や教頭たちに挟まれてストレスが溜まる一方じゃないですか」
「そりゃあそうですがね」
「だからその解消ですよ。目の保養ですな。先生だって女に興味がないわけじゃない
でしょうに」
「いやあ……、そうですね、私なんかはどっちかというと、ほら、新任の中西先生。
ああいう方がいいですな。こう、しっとりしてるようで、どっか抜けてるところが
また可愛い」
「ああ、中西……智里とかいいましたかな? まあ悪かないですが、やっぱり私は
もっと若い方がいいですな。若いというか青い感じかなあ」
「……」
田中教諭の声が途切れた。
呆れているのだろう。
高校の教師なのに、こうもあからさまに女生徒へ性的な関心を示すというのはまずい。
実際、父親と娘ほどの年の差があるのだ。
縦しんばそういう邪な思いを持っていたとしても、しゃあしゃあとそれを他人に話す
という神経がわからない。
その様子を窺いながら、禎一は蘭を犯していく。
「あ……、うむ……」
蘭はきつい挿入感に身を捩って呻いている。
禎一はそんな蘭を見ながら腰を打ち込んでいった。
途端に蘭が暴れ出す。
「やっ、やめて、こんな時にっ……ああっ……」
「おいおい、あんま声あげんなよ。聞こえちまうぜ、嵯峨島の野郎によ」
「……!!」
蘭はハッとして口をつぐむ。
誰に見られてもイヤだが、嵯峨島は特にお断りだ。
こんなところを見られたら、何を言われるかわからない。
いや、言われるだけでなく何かされるかも知れない。
なのに禎一は腰を突き込んでくる。
「くっ……んんっ……はああっ……」
蘭は顔を真っ赤にして呻いた。
懸命に唇を噛みしめても、すぐに緩んで荒く息を吐き、呻き声が漏れる。
きざしてくる妖しい感覚を振り払おうと顔を左右に振りたくっていた。
「嫌がってる割りにはよく締まるな。感じてるのか?」
「ち、違……んあっ……」
「やっぱ蘭はマゾだな。こういう場所でやられたり、外に誰かいるって状況で犯される
と感じて感じてしようがないんだろうが」
違うという風に、蘭は強く首を振った。
それでも、次第にその肉体は燃え上がっていく。
禎一に言われた通り、誰かに見られるかも知れないことに興奮し、感じてしまう。
いつも犯されている時以上に燃えてくるのがわかる。
「あ、ああ……いやあ……やめて、もう……もう、ここではいや……あ……」
「ここでなければいいのか? え、ここでなければ何されてもいいのかよ」
蘭は何度も頷いた。
「こ、ここではいやなの……、あ、あの先生がいるところではいや……他の人がいる
ところじゃいやよ……ああ……」
禎一は言葉で追い詰めながら、腰の動きも緩めない。
激しく突き上げる感じではないが、奥の方に入れてぐりぐりと抉るように腰を使って
きた。
片手は、剥き出しになっている蘭の乳房をやんわりと揉み上げている。
「何でもするんだな」
「し、します……何でもするから、もう……ああっ……」
「じゃあ、口でも尻でも嫌がらずに受け入れるんだな」
「そっ、それは……」
「そうか。じゃあ続行だ」
「やっ……、ま、待って、お願いっ……!」
「もう遅い。最後までやってやる」
「い、いやっ……!」
いつしか蘭の肌には汗が浮き、匂うようなピンク色に染まってきている。
乳房を鷲掴みにされ、揉みしだかれていると、次第に乳首が尖ってきた。
乳輪をつままれ、乳首をこねくられると、もう何もかも忘れて大声で喘ぎたくなる。
もちろんその間も禎一が腰を打ち込み続け、蘭の媚肉を抉ってきていた。
「……蘭もだいぶセックスに馴れてきた感じだね。いきなりなのに、簡単に俺のものを
飲み込めるようになってきた」
「違う……そんなんじゃない……ああ……」
「そうかな。蘭だって前よりもずっと感じるようになってきたんだろう?」
「そんなこと……、そ、それは、ああ……か、身体が……ああ、馴れちゃったから、
です……あう……」
心まではまだ堕ちていない、と言いたいのだろう。
しかし、まったくの処女だった肉体の方は、僅かな期間のうちに驚くほど性行為に
馴染み、成長していっている。
何度も何度もセックスを挑まれているうちに、蘭の声は呻き声から喘ぎに変わり、
その喘ぎも次第に大きくなっていったのだ。
精神の方も、少しずつセックスにのめり込みつつある証拠だ。
さらに、虐められ、辱められることに背徳的な快楽を覚えてしまうという因果な体質も
大きく影響しているだろう。
「ああ……ああっ……だ、だめ……こ、声……出ちゃう……」
「あんまり派手に喘ぐなよ、バレるぜ」
「い、いや……、ああ、もうやめて……んんっ……」
蘭が快楽を押さえ込み、よがる声を堪えている最中でも、外では嵯峨島の脳天気で
ふしだらな会話が続いている。
「最近は女子高生と言えども、おとな顔負けのプロポーションのやつも多いですからな。
スクール水着とはいえ、見とれるほどの女もいますよ」
「……」
「例えばね、先生は学年主任だからご存じでしょう。二年に毛利蘭てのがいるでしょう」
「ああ……、空手部の」
「そうそう。あれなんかいいですぜ。私ゃ部活の時に何度か空手部にもプール貸したん
ですが、その時に見た毛利の水着姿……、いやあよかったですよ。たまらんかったですな」
「先生……」
「あんなのを見れば、そりゃあ何とかしたいと思いもしますって」
「先生、冗談でもそういうことは……」
「わかってますよ。でも、こないだやつとふたりっきりになる機会があったんですが、
つい「過ち」を犯しそうになりましたな」
そう言った嵯峨島は下品に「がはは」と笑った。
「くくっ、聞いたか蘭。あの変態教師、おまえに欲情してるらしいぞ」
「い、いやっ……」
蘭も少なからずショックを受けていた。
嵯峨島が他の女生徒に色目を使っているのはしていたし、自分に対してもそういう目で
見ているらしいことも承知していた。
しかし、本人の口からああもはっきりと、淫らな欲望を隠そうともしない言動をする
とは思わなかった。
大嫌いな男にそこまで言われ、蘭は悪寒が走ると同時に、ゾクゾクするような痺れも
感じていた。
「あっ、ああっ……深い、そんなっ……」
「気持ち良いからってそんなに喘ぐなって。それとも嵯峨島に聞かせるつもりなのか?」
「いやっ……」
「そんなに嫌いか、蘭。あの先公は」
「き、嫌いです……。い、いや、あんな先生……」
「そうか。嵯峨島に抱かれたいとは思わないのか」
「ぜ、絶対にいやですっ」
「ふうん。だがおまえは嫌なことをされると燃えるんだろ? だったらやつに犯され
ればたまらねえほどいいこかも知れないぜ」
「そ、そんなこと言わないでっ……あああ……」
言葉で虐められるたびに、蘭の性感が高まっていく。
官能の淫らな炎が、次第に燃え盛ってくるのが自分でもわかるのだ。
禎一はそんな蘭の腰を掴み、強く打ち付けていく。
勢い余った乳房がゆさっ、ゆさっと大きく揺れた。
蘭は次第に快楽に巻き込まれていった。
(か、感じちゃだめっ……こんな時に気持ち良くなっちゃだめっ……で、でも、ああっ
……もう……)
見透かしたように禎一が小声で囁く。
「感じるんだろ、蘭」
「……」
ふるふると顔を振って否定する蘭だが、その動きはぎこちなく弱々しかった。
「それじゃもっと感じさせてやるか」
「い、いやっ……ああっ!」
乳房を両手で揉み抜かれながら、何度も何度も長いストロークで腰が叩きつけられる。
禎一の腰と蘭の尻がぶつかって、ぴしゃぴしゃ言う音が外に漏れないか、蘭は気が気
ではない。
青い少女の肢体から徐々におとなの成熟した肉体に変化していく過程の少女の身体は、
セックスされることで急速に熟れていった。
その肢体をうねらせ、押し寄せる肉の快楽に抵抗している蘭の身体を禎一は責め続けた。
「あ、あっ……もっ、あっ……こ、声……出ちゃいますっ……」
「出せばいいだろう。嵯峨島に聞かせてやれよ」
「そんな、いやっ……」
「じゃあ黙ってるんだな」
「そんな……、だ、だったら、もうしないで……やめてください……ああ……」
「そうはいかんさ。俺がいくまではな」
「で、でも、このままされたら……我慢できなくなっちゃいます……ああっ!」
つい大きく喘いでしまい、さすがに禎一も蘭の口を塞いだ。
蘭に喘ぎを我慢させるのは愉しいが、あまりに大声でよがられてはバレてしまう。
いくら禎一でも、この場で教師たちの前に晒すつもりはない。
「おい、バラすつもりかよ。大声で喘ぐな」
「ああっ、そ、そんなこと言われても……だ、だめ、あうう……声が出る……もう声が
出ちゃいますっ……」
「どうすりゃいいんだよ」
「く……口を塞いで」
「生憎、両手は蘭のおっぱい揉むので忙しくてな」
「そんな……」
蘭は泣きそうな顔になった。
しかし、こんなに虐められているのに、媚肉はじくじくと蜜を分泌し、蘭の太腿にまで
垂れてきている。
膣を貫く肉棒の威力も一向に弱まらない。
素早いピストンではないものの、ずぶっ、ずぶっと一回一回が重く、力強い突き込み
だった。
「あっ……あうっ……だ、だめっ……声が……く、口を塞いでっ……ああっ」
「どうやって」
「くあっ……く、口で……森さんの、口でっ……いっ……ああっ……」
「口? キスして欲しいのかな?」
蘭はガクガクと頷いた。
普段は一方的かつ強引に禎一が唇を奪うだけだった。
こんなになっても、まだ新一のことを想っている蘭は、思わず肉の欲望に負けて禎一に
身体を自由にさせることはあっても、決して自分からキスを求めることだけはなかった。
ただ犯されるよりもキスの方が一層に罪深く、新一に対して申し訳ないという背徳感が
強かったためだ。
それを自分から求めなくてはならない。
蘭の心は千々に乱れ、爛れていった。
「は、早く……声が出るっ……キス、してっ……ああっ……」
「ふふ、そんなにキスしたいならしてあげるよ」
「んっ……んちゅっ……」
半開きになった蘭の口に、禎一の口が吸い付いていく。
もう禎一の舌が咥内を蹂躙することに抵抗はない。
嫌がっていたら口を離されるかも知れない。
口の中を動き回る男の舌に鳥肌を立てながら、蘭は懸命に堪えていた。
「んむっ……んんんっ……んうっ……じゅっ……ちゅううっ……んむむう……」
これで遠慮なく喘げると思ったわけではないだろうが、蘭は禎一の口の中で喘ぎ始めた。
もしキスで口を塞がれていなければ、大きく口を開けてよがっていただろう。
乳を揉まれ、膣を犯される快感はどんどん体内に溜まっていき、声でも出さなければ
解放できないのだ。
気持ち良くなると喘ぎ、身体をうねらせ、よがらずにはいられないのは、そうした理由
である。
逆に言えば、声を出させず、身体も動けないようにしてしまえば、女の快楽は高まる
一方になる。
溜まりに溜まった状態まで持っていって、一気に解放させれば、女はこれ以上ない至上
の喜悦を得ることが出来る。
「んんん……んむ……んちゅっ……はうむ……」
キスされることで、さらに蘭の性感が上昇していく。
こうなることは蘭自身わかっていた。
いやなのに、口づけされるとゾクゾクするような痺れが背筋に走る。
特にセックスされながらキスされると、一気に頂点までいってしまうこともあった。
禎一の舌が蘭の咥内粘膜をこそぐように擦っていく。
その舌を追うようにして、蘭自身から舌を絡めていくのだった。
また声が聞こえてくる。
田中教諭だ。
「しかしですな、嵯峨島先生。こりゃここだけの話ですがね、どうもまずいですよ。
噂ですが、先生の行状が上へ漏れてる可能性がある」
「上? 校長とかですか?」
「ええ、それだけじゃないですが。どうも生徒かその親が訴え出たのか、あるいは
見ていた生徒がチクッたのか……」
「そうですか……」
嵯峨島は内心舌打ちした。
最近は女房との間もぎくしゃくしているし、どうもツキがなかった。
おかしなことに、妻の方まで嵯峨島の学校での猥褻行為を知っているようなフシが
あったのだ。
そのせいで妻まで嵯峨島を軽蔑していた。
そこでチャイムが鳴った。
田中はホッとしたように嵯峨島を促した。
「予鈴ですよ、もう行きましょう先生」
それを合図にふたりの教師は出て行った。
扉が開閉する音が響くのを最後に、再びトイレ内は静かになる。
禎一は口を離して言った。
「……バレなくてよかったな。嵯峨島、行っちまったぜ」
「ああ……」
蘭はホッとしたように肩を落としたが、腰が蠢いている。
律動を止めてしまった禎一の腰に、自分から押しつけるようにもぞもぞと動く。
「なんだ、それは。やめて欲しいんじゃないのか?」
「……」
「それとも、もっと犯して欲しいのか? なら、そう言え」
「ああ……」
蘭は顔を俯かせ、小さく呻いたものの、すぐにまた顔を上げた。
禎一ですら、ぞくっとするほどの妖しい色香を漂わせている。
そして、潤みきった瞳で禎一を見て言った。
「し……して……」
「何をだ」
「い、意地悪……わかってるくせに……」
もう恋人同士のような会話になっていることに、蘭は気づいていない。
禎一はにやにやしながら言った。
「わからないよ。ちゃんと言って」
「だ、だから……最後まで、して……」
「セックスして欲しいんだな? こんなところで、トイレの中で犯して欲しい、と」
「ああ……」
蘭はコクンと頷いた。
今までならともかく、肉体的に成熟しかかっている蘭の身体は、こんな中途半端な
状態で放っておかれたらどうにかなってしまいそうだ。
なまじ、本当にこれで終わりにされたら、隠れて校内でオナニーしてしまいそうな
くらいに追い込まれている。
「そうか。蘭はセックスして欲しいんだな。もう午後の授業が始まってるのに」
「そ……そうです。せ、セックス……して……犯してください……ああ……」
「よしよし、だんだん素直になっていくね」
禎一はそう言って腰の動きを再開した。
それまでとは打って変わった激しい打ち込みだ。
誰もいなくなったことで遠慮がなくなった。
「ひあっ、いっ、いいっ……あ、待って、強すぎるっ……は、激しいっ……ああっ!」
蘭が「いい」と口にしたのは初めてだった。
もしかすると、さっきのキスの最中に禎一の口の中で言っていたかも知れないが、
いずれにせよ今日が初めてだ。
禎一は、愉悦の表現が露わになっていく美少女に興奮し、激しく抽送を繰り返した。
同時に乳首をこねくり、乳房を強く揉んでいく。
「くうっ……!」
蘭が顔をしかめた。
まだ乳房は強く揉まれると痛いようだ。
無理もない。
胸は女の急所だ。
しかしこれも時間の問題だろう。
この敏感な少女なら、すぐに強い愛撫に反応するようになる。
「あ、あう、いいっ……くっ……ああ、いいっ……」
「そんなにいいのか、蘭」
「いいっ……」
蘭は何度も頷いた。
もう、白昼の学校のトイレで授業中に犯されている、ということなど忘れている。
今はただひたすら、込み上げてくる肉の快楽を貪っていた。
「蘭、ほら」
「ああ……」
禎一が顔を近づけ、口から舌を伸ばすと、蘭も応えるように舌を伸ばしてきた。
そして口から出した舌同士をちょんちょんと接触させ、絡め合っていく。
また蘭に背徳的な被虐の官能が打ち寄せてくる。
口から舌を出して絡め合うことは、ただのキスよりも一層に淫らな気がした。
そうやってしばらく舌の交歓をしてから、禎一は本格的に責め出した。
今度は自分が気持ち良くなるためだ。
「あっ、あはっ、いっ……ああ、もうだめっ……あ、あたし、またっ……!」
「いきそうなのか?」
蘭はガクガクと何度も頷いた。
「い、いきそうっ……もういきそうなんですっ……ああっ……」
禎一が命令せずとも、蘭ははっきりとそう口にした。
精神的にはともかく、肉体的には陥落寸前だ。
蘭の美しい肢体には玉のような汗が浮き、突き上げられるたびにそれが飛び散って
いる。
カッターシャツは汗でへばりつき、うなじや額の髪の生え際にも、びっしりと汗が
浮いていた。
蘭の膣が急速かつ強烈に締まり、禎一も快感に呻きながら腰を使っていく。
「お、おっ……くっ、すげえ……やっぱおまえすげえぜ、大したオマンコだ」
「あ、あひっ……ひっ……い、いく……いきそっ……ああっ……」
蘭を壁に押しつけるほどにグイグイと力強く突き込んでやると、蘭はいっそうに
よがり、絶頂寸前となっていく。
きゅうきゅうと収縮する蘭の媚肉の素晴らしさに、禎一も耐えきれなくなった。
「くっ、蘭、もういくぞ! おまえもいくんだ!」
「は、はいっ……あ、いく、いきそうっ……」
「中に出すからな!」
「だ、だめっ、ああ、中はやめてっ……」
まだ膣内射精されるのは抵抗があるようだ。
当たり前のことで、そんなことをされ続けたら、いつか妊娠してしまうだろう。
しかし蘭は、最初のうちこそ本気で嫌がっていたものの、ここのところ中に出されると
やけにとろけた表情をするようになっている。
心ではまだ膣内射精に対する嫌悪感と恐怖、絶望があるのだろうが、身体の方は、
男の精を受ける感覚に対して馴染み、それを愉悦と判断するようになっているのかも
知れない。
「だめだ、中だ。蘭は俺のものだ、だから中に出すんだ」
「だ、だめ、そんなっ……あたしは新一の……ああ、いいっ……ひっ、あ、もう……
もうっ……」
「くうっ!!」
そこで蘭は激しく絶頂し、大きく背中を反り返らせた。
縛られた両手がぐぐっと握りしめられ、びくびくっと何度も身体を震わせた。
食いちぎられるかと思うほどにペニスを締め付けられた禎一も、思い切り蘭の尻に腰を
押しつけてから、一気に射精してのけた。
びゅるるっ、びゅうっ。
どびゅっ、どびゅびゅっ。
どくっ、どくどくどくっ。
熱くて粘っこい精液の感触をモロに粘膜に感じて、蘭はわなわなと痙攣しながら喘いだ。
「んああっ、で、出てるっ……あ、あ、また……また中に出された、あうう……」
禎一は射精するたびに、ぐっと蘭の腰を抱え自分の腰を押しつけていく。
尻を潰しながらびゅくびゅくと射精し続けた。
びゅく、びゅくっ。
どぷっ、どぷっ。
びゅるっ。
びゅるんっ。
「あ、あうう、まだ出てる……もういや……中は、ああ……あ、何かヘン……あ、いき
そう……またいくっ!」
射精を膣に受け続け、精液に胎内を穢される感触で、蘭はまた気をやった。
熱くて濃い精液を引っかけられる物理的な刺激とともに、また恋人以外の精液で胎内を
犯されてしまったという被虐感の相乗効果だった。
蘭の媚肉はまだ肉棒を締め付けている。
まるで全部精液を出すまで許さない、とでも言っているかのようだ。
ぶるぶる震えていた蘭の尻から、禎一がゆっくりと肉棒を抜いていく。
「あう……」
ペニスを引き抜かれると、蘭はまるで芯が抜けたかのようにがっくりと項垂れ、膝が
崩れた。
抜かれたペニスは、禎一の精液と蘭の愛液でぬらぬらと淫らに光り、今にも湯気が立ち
そうなほどに熱かった。
彼の精力からすれば、まだまだである。
しかし、もう授業は始まっており、ここでまた続けて蘭を犯していては、さすがに
まずいだろう。
禎一は、力の入らない蘭のロープを解き、立ち上がらせた。
「あ……」
「満足したか?」
「……」
「ふん。終わると素直さがなくなるな。ま、いい。それより、もう教室へ戻れ」
「は……い……」
蘭はのろのろと制服の乱れを直していく。
膝が笑い、がくんと倒れそうになっていた。
それを支えながら、禎一は蘭のショーツを引き上げていく。
「あ……、何を……」
「何って、履かせるんだよ。ノーパンでいいのか?」
「違いますけど……でも……」
股間が汚れて気持ち悪い。
膣からは、たらりたらりと多すぎる精液が零れ出ている。
履くにしてもそのままにしても、股間を洗うか、少なくとも拭わないと気持ちが悪い。
蘭がトイレットペーパーを巻き取っていると、禎一は構わずショーツを腰まで引き
上げてしまった。
さすがに蘭は慌てて禎一の手を押さえた。
「あ、だめっ……何するんですか!」
「……」
禎一は無言で蘭の手を払い除け、そのままショーツを思い切り引き上げてしまう。
当然のように、膣から漏れた精液が蘭の下着に大きな染みを作り、それがどんどんと
広がっていく。
それに構わず、禎一は蘭の顔を見下ろして言った。
「このままでいろ。脱ぐことは許さない」
「そんな……、だって……」
「許さない」
「……」
「もう行け」
諦めたのか、蘭は小さくため息をついてスカートを下ろした。
プリーツの入ったスカートは膝まで隠してくれてはいるが、蘭は気になって仕方が
ないようだ。
やはり精液がどんどん漏れてくるのだろう。
腰や膝をもじもじさせながら禎一にすがるような視線を寄せていたが、それを冷たい
目で返されると、がっくりと項垂れたままトイレを出て行った。
──────────────────
───あ……、新一? ごめん、突然……。……うん、そうでしょ。あたし……、
今、元気ないんだ……。
───……だから、それは電話では言いにくい……、言えないの。うん。うん、そう
……かな。
───だから会いたいの。会って欲しいの。……何かおかしいって? ……うん、
おかしいかも知れない。
───ね、聞いて、新一。あたし……、あたしもうダメ……。だめになりそうなのよ。
───もうね……、もう、どうにもならないの。会いたい……会いたいよ、新一。
───……助けて。お願いよ、助けて新一……。あたし、このままじゃおかしく
なっちゃう……。
───すぐ。すぐに来て。ああ、あたし、行かなきゃ。またあそこに行かなきゃ
ならないの。でも行きたくない。行きたくないけど……。
───場所? ……。
───……言うわ。あのね、ほら、米花の東の端っこに廃工場の跡地があったじゃ
ない。うん、そこ。あそこ、新しくビルが建つみたいなこと言ってたけど、
結局、そのままになっててさ、今は鉄条網で囲ってあるだけの空き地みたいに
なってるの。そこに大きなプレハブが……、あっ!
も、森さんっ、何で……? ち、違います、警察なんかに電話してませんっ。
これは……、ああっ!
───し、新一っ、新一っ……、助け…… プッ ツーーーー……
戻る 作品トップへ 第四話へ 第六話へ