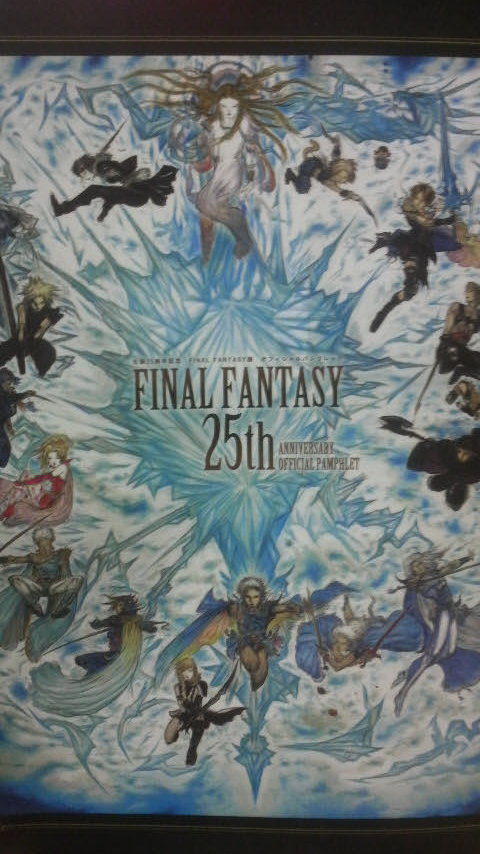[ジタスコ]優しい記憶を君に送る
- 2012/09/08 21:19
- カテゴリー:FF
花が好き、らしい。
と言うのは、ジタンの観察による思い込みなのかも知れないが、しかし、彼が花を見ると微かに頬を綻ばせるのも確かであった。
「好きなのか」と問えば「別に」と素っ気ない反応しかなかったけれど、彼が素直に自分の感情を認める性質でない事を、ジタンは重々承知している。
だが、ジタンは自分の観察による答えが、強ち間違いではないだろうと確信していた。
(まあ、意外だなとは思ったけど)
聖域から然程遠くない場所に、ぽっかりと開いた湖がある。
その周辺は、秩序の女神の恩恵を受けているのかは判らないが、魔物の気配もなく、戦士達の小休止にも丁度良い。
可惜に人が来る事もない(何せこの世界の住人は、総勢合わせても二十人程度だ)為、その空間が酷く荒れてしまう事もなく、湖を囲うように咲き誇る花々も、穏やかな時を過ごしていた。
時折、ティナやルーネスが花冠を作る為に摘む事があるが、それも必要以上の事ではないし、花に少女と言う組み合わせならば許されても良いだろうと、ジタンは思う。
ジタンは今、その花畑の中にいた。
ティナとルーネスに教わった、花冠を作りながら。
「……意外と難しいもんだな……」
手先は器用な方────と言うより、絶対に器用であると自負しているのだが、中々上手く作れない。
ティナとルーネスに手解きして貰っている時は、お礼にとティナには冠と髪飾りを、ルーネスにもブレスレットにして贈れる位には、それなりに良い出来に仕上げられた筈なのだが、今のジタンの手の中にあるものは、辛うじて花輪らしく見える程度。
とてもではないが、贈り物として人の手に渡せるようなものではない。
少なくとも、ジタンが思い描く理想像には程遠かった。
もう花冠なんて凝ったものにしないで、花束にして渡した方が良いだろうか。
そう考えもしたが、花束なんてそれこそ迷惑がられるだけだろう。
現実的な思考を徹底させている彼の事だから、こんなものがあっても直ぐに萎れさせてしまうだけだとか、食用に出来るのならまだ良いが、なんて台詞が帰って来そうで、色気も何もあったものではない。
別段、大切にして欲しいだとか、特別に愛でて欲しいとか、そういうつもりで渡す気はないのだけれど、やはりもう少し────嬉しそうな反応を見てみたい、と思う。
普段、滅多に笑った顔など見せてはくれない相手だから、尚の事。
「あー…でも、それだったらもっと別の物にした方が良かったかなー」
誰に対してでもなく呟いて、ジタンは空を仰いだ。
手の中には歪に繋がった花の連なりがあって、とてもではないが花冠などと上等な呼び名では括れそうにない。
こんな歪な花の輪っかより、砥石とか、弾薬の材料になりそうな素材とかの方が喜ばれる気がする。
それなら幾ら渡しても困るものではないだろうし、必要なものであるから、彼も素直に受け取ってくれるだろう。
戦場で男に渡す贈り物としては、絶対に場違いなものだと、手の中の儚い命を握って思う。
けれど、摘んでしまった以上、このままポイと捨ててしまっては、それこそ自分が酷い男になってしまう。
彼が喜んでくれるのか否か、今は考えるのは止そう。
贈り物と言うものは、贈る側の気持ちが重要なのだ、そう、大切なのは気持ちを渡す事だ。
そんな呪文を心の中で繰り返し、言い聞かせながら、ジタンは冠づくりを再開させた。
………再開、させようとした。
「─────ジタンか?」
己の名を呼ぶ低い声に、ジタンの尻尾が思わず直立した。
まさかと言う思いで振り返ってみれば、青灰色の瞳が花畑の外縁で、ジタンを見詰めていた。
「ス、スコールか。びっくりしたぜ」
「……悪かったな」
ジタンの言葉に、スコールが判り易く顔を顰める。
間の悪い時に来てしまった、と思ったのであろうスコールに、ジタンは慌ててそんなことない、と手を振った。
「いや、オレが気付かなかっただけだよ」
「…あんたが人の気配に気付かないなんて、珍しい事もあるんだな」
「ちょっと集中してたからさ」
ふぅん、とスコールは気のない反応を零すと、ジタンから少し距離を置いた場所に腰を下ろした。
それきり、傍らにあるジタンの存在も忘れたように、風に揺れる花弁の群れを見詰めて口を噤む。
ジタンは、隣の存在をこっそりと意識しつつも、冠作りを今度こそ再開させようとした。
が、渡したい相手の目の前で作るってどうなんだ?と茎を編もうとした手が止まる。
そもそも、彼が花を贈られて喜ぶだろうかと言う疑問も、もう一度浮かんできて、ジタンは完全に作業を停止させた。
「……なあ、スコール。ちょっといいか?」
ジタンが声をかけると、スコールは少しの間を置いてから、此方へと向き直った。
その動きが、いつもの整然とした無駄のないものとは違い、何処か夢うつつのような、ぼんやりとしたものに見える。
ジタンは頭を掻いて、一拍の間を置いてから、尋ねた。
「スコールって、花、好きか?」
「……なんだ、突然」
「いや、さ。割とよく、此処に来てるみたいだったから」
「……静かだからな」
騒がさを嫌うスコールにとって、静寂と言うものは重要なものだ。
だから今のスコールの返事は、ジタンにとっても予測できたものだった。
ただ静かな場所を求めるだけなら、ホームである屋敷の自室や、一人で見回りも兼ねて出掛けるとか────とジタンは思ったが、自室では賑やか組(無論ジタンも含む)の襲撃があるし、聖域から離れないとは言え、単独行動を取れば後でウォーリアが何を言い出すか。
聖域からこの湖まででも、一人で行き来するのはあまり褒められた行動ではないが、この湖は聖域のほど近い場所から肉眼で確認できる程度の距離だ。
異常があれば、或いは混沌の戦士の気配があれば、聖域に残っている誰かが直ぐに気付く事が出来るだろう。
だからスコールの先の言葉でも、十分に、彼がこの地へ足を運ぶ理由にはなるのだが、
「うん、まあ、そうだろうけど。花の方は、どうでも良いのか?」
時折、ジタンとバッツと共に、散歩と称してこの湖に来る度、スコールは花畑の中で何をするでもなく過ごしている。
湖の中ではしゃぐ二人の仲間を、呆れた表情で眺めている事もあるが、それ以外では、ひっそりと咲いた花をじっと見詰めている。
その表情は、いつもの冷静沈着な、大人びた傭兵のものとは違い、年相応の少年らしい綻びを見せていた。
まるで大切な何かに触れるように、そっと手を伸ばして花弁に触れ、酷く優しい笑みを浮かべるのだ────ほんの一瞬だけではあるけれど。
だから花が好きなのではないかと、或いは花に対する何か特別な思い出があるのではないかと、ジタンは思っていたのだが、
「……さあ。よく判らない」
肯定でも否定でもない、曖昧な答えに、ジタンは「おや?」と首を傾げた。
「花、好きなんじゃないのか?」
「…別に。嫌いじゃないとは思うけどな。ティナやフリオニールには悪いが、どうでも良いと言うか」
スコールの言葉に、ジタンは手元の冠の欠片を隠した。
当てが外れて、出鼻を挫かれた気分だったのだ。
スコールはそんなジタンの様子には気付かず、地面に杖にした腕の傍に咲いていた花を見た。
そうして彼の唇が、笑むように綻ぶから、ジタンはてっきり、彼が花が好きなのだとばかり思っていた。
違うのなら、どうしてそんな表情をするのだろう。
そう思っていたら、答えは彼の方からやって来た。
「でも、多分、何か────あったんだと思う。思い出せないけど、何か」
何か。
そう言って、スコールは小さく微笑んだ。
明瞭ではない記憶の中で、それでも温もりを感じる、何か。
自覚のないまま、口元が綻ぶくらいの、温かな“何か”。
「そっか」
「……変な話だけどな」
「そんな事ないさ」
馬鹿みたいだろう、と言いかけたスコールの言葉を遮って、ジタンは言った。
「思い出せなくたって、覚えてるんだ」
「思い出せないなら、覚えていないって事だろう」
「記憶の話じゃない。心が覚えてるって事だよ」
スコールが顔を上げて、ジタンを見た。
見詰める青灰色に、ジタンは笑いかけてやる。
「良かったじゃん。きっと、すごく嬉しい思い出だったんだろ。大事にしろよ、そういうの」
スコールが、ウォーリアやルーネス同様、殆どの記憶が欠けたままである事を、ジタンは知っている。
だからこそ、微かに蘇る記憶の欠片が、彼にとってとても大切な“自分自身”の一欠けらである事を、ジタンは理解していた。
その断片の、とても優しい部分を掬い上げる事が出来たのなら、それは大切にするべきだ。
スコール自身の、とても優しい一欠けらなのだから。
ジタンの言葉に、スコールは驚いたように目を丸くしていた。
それから、小さな小さな声で「……そうだな」と言って笑みを零す。
そんな風に笑ってくれる彼の思い出の中に、自分の存在があったら、どんなに嬉しい事だろう。
ジタンは、手の中に隠していた、花冠を想い人へと差し出した。
ジタスコの筈なんだが、話が大分逸れた気がせんでもない。
しかしジタスコだと言い張る。
FF界一の男前なジタンが好きです。
スコールはどうしてもネガティブな思考を持ちそうなので、前向きで良い意味で欲張りなジタンに引っ張って行って貰ったら良いと思う。